歴史と民俗 既刊目次
※論文のデータベースは「神奈川大学デジタルアーカイブ」で検索可能です。
歴史と民俗22〈2006.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集22
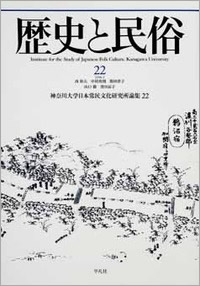
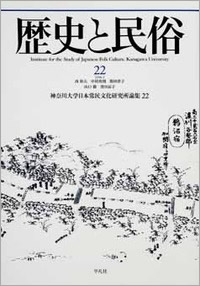
中山道鵜沼宿の幕末期の様相—建物の復原検討を中心に(西和夫)
オーラル・ヒストリーの可能性—満州移民体験を中心に(中村政則)
第8回常民文化研究講座報告 身体表現としての芸能とその継承
(廣田律子)
[資料紹介]中村為治・満蒙開拓従軍紀行(山口徹)
アチックミューゼアム日誌(4)昭和13年・14年・15年1月~6月
歴史と民俗21〈2005.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集21
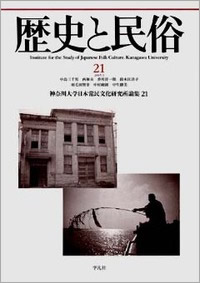
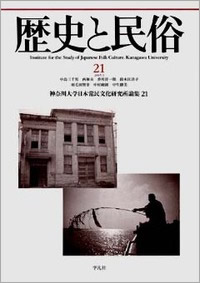
明治天皇の大喪と台湾—代替わり儀式と帝国の形成(中島三千男)
文化財指定の問題点、そして庶民文化財の試み(西和夫)
海人のむらの民俗誌から(中)—宇久島・平調査ノート
(香月洋一郎)
浜波太漁業組合の成立と役割—残存史料の再検討から(鈴木江津子)
ふたつの「距離」と民俗展示—さわれる展示を通して(羽毛田智幸)
資料紹介 加藤完治・満州移民の戦後史(中村政則)
GHQと民族学・民俗学—民族学振興会文書に見る戦中・戦後の学術界(中生勝美)
追悼 網野善彦氏の逝去を悼む
歴史と民俗20〈2004.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集20
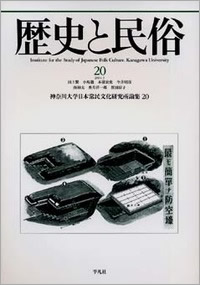
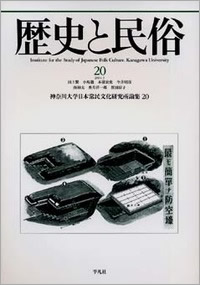
近世神社領の土地管理組織—大山崎離宮八幡宮領を事例として
(田上繁)
「さかい」の論理と「あいだ」の論理—言語の人類学的側面
(小馬徹)
「軍神」空閑少佐再考—捕虜
自決をめぐる言説と伝承(本康宏史)
忠霊塔に関する一考察—その意匠と祭祀形態をめぐって
(今井昭彦)
防空壕(西和夫)
海人のむらの民俗誌から(上)—宇久島・平調査ノート
(香月洋一郎)
資料紹介 アンチックミューゼアム日誌(3)昭和12年1月~12月
歴史と民俗19〈2003.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集19


第六回常民文化研究講座 はじめに(香月洋一郎)
宮本勢助・馨太郎 民具研究の軌跡(宮本瑞夫)
早川幸太郎のアチック時代(須藤功)
記録する農・漁民(香月洋一郎)
文書館にかけた夢—宇野脩平の人と業績(橘川俊忠)
則民去私の人・河岡武春—『民具マンスリー』の周辺(佐野賢治)
クシャミの比較民俗学—キプシギス文化を中心に(小馬徹)
『南游』に唱われた地獄(廣田律子)
フィールドとしての地籍図(香月洋一郎)
地域社会と映像メディア—昭和30年代から40年代にかけての長野県阿智村を事例として(矢野敬一)
祭礼と女性—小倉祇園太鼓におけるジェンダーをめぐる言説の変遷から(中野紀和)
海女の磯資源利用と進行(李善愛)
資料紹介『古海の郷』(抄)(北村肇)
歴史と民俗18〈2002.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集18
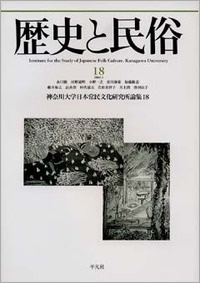
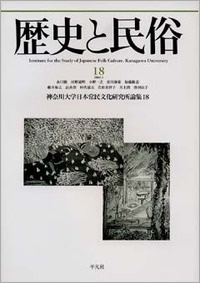
第五回常民文化研究講座の開催趣旨(河野通明)
民具研究と日本常民文化研究所(山口徹)
博物館活動と四季耕作図研究—四季耕作図研究の過去・現在そして将来(河野通明)
幕末外国人の日本スケッチと四季耕作図研究(小野一之)
守屋家掛幅と四季耕作図研究(佐川和裕)
「描かれた農耕の世界」展の経験から(加藤隆志)
摂津の四季耕作図—月次絵の継承と展開(藤井裕之)
描かれた水口祭り・焼米搗き(畠山豊)
二神家墓地調査中間報告(田代郁夫・若松美智子)
「修学旅行記」にみる渋沢敬三の学問的基礎過程(井上潤)
資料紹介 アチックミュージアム日誌(2)昭和11年1月~12月
歴史と民俗17〈2001.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集17
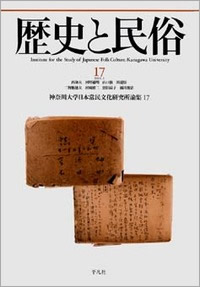
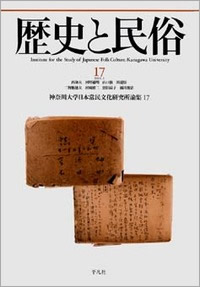
町並み調査と町の再生—平戸市(長崎県)の場合(西和夫)
中林湘雲筆「四季耕作図屏風」の基礎的検討(河野通明)
第四回常民文化研究講座を迎えるにあたって(所長 橘川俊忠)
漁業における歴史と民俗(山口徹)
漁村の民俗世界(田邉悟)
戦後世代旧日本常民文化研究所の漁業史研究(二野瓶徳夫)
猿回しの人生—村崎修二氏の公演から(村崎修二 編集 香月洋一郎)
追悼 宮田登氏の逝去を悼む
資料紹介 アチック・ミュージアム日誌(1)昭和10年9月~12月
歴史と民俗16〈2000.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集16
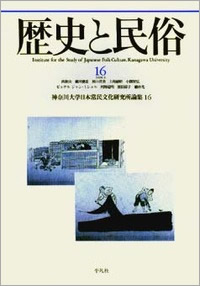
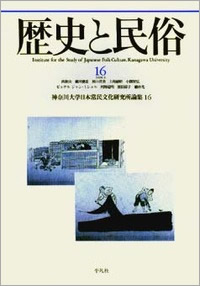
日本の鋸、その歴史と現状—「中や久作」の検討を中心に(西和夫)
近世能登・加賀に流通した書籍—屏風の下張りになった「書物通」から(橘川俊忠)
現代のマタギ(田口洋美)
大道芸と現代(上島敏昭)
町工場における技術伝承(小関智弘)
「悪魔が妻を殴って、娘を嫁にやる(する)」—フランス語の「狐の嫁入り」と民俗伝承(ビュテル ジャン・ミシェル)
西川祐信『絵本士農工商』農之部とその影響(河野通明)
『絵引』成立過程についての一考察(1) —日本常民文化研究所所蔵資料から(窪田涼子)
中国仮面の歴史(顧朴光著・廣田律子訳)
歴史と民俗15〈1999.3〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集15
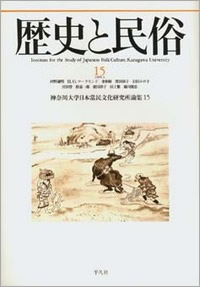
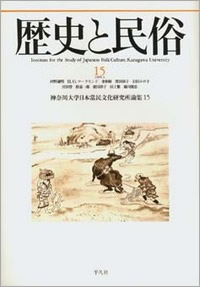
常民研本「四季耕作子供遊戯図巻」の成立(河野通明)
成仏狩り—日本の神仏習合の一例(H・O・ロータモンド)
韓・日世間話の比較研究(金和経)
戦国期の在地寺院と地域社会(窪田涼子)
天保期における寄場組合村大惣代と関東取締出役との情報交換の実態と特質—武州足立郡新染谷村守富家文書から(岩田みゆき)
富士信仰研究進展のために—『富士吉田市史』第五巻近世Ⅲの発刊に寄せて(宮田登)
私とアチック・ミューゼアム(拵嘉一郎(述))
『陳十四夫人伝』に唄われた地獄(廣田律子)
京都大山崎調査報告(1997年度)(田上繁)
奥能登調査の経過と残された課題(橘川俊忠)
歴史と民俗14〈1997.9〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集14
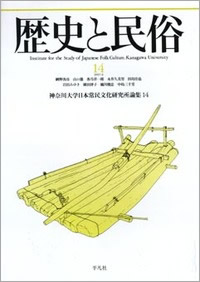
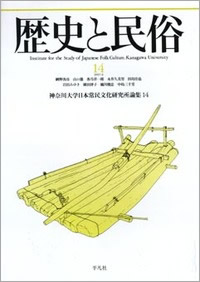
日本中世の桑と養蚕(網野善彦)
絵画・「モノ」史料論—史料学を考える一つの試み(山口徹)
慶尚北道羅北の筏船とワカメ漁—韓国漁業調査ノート1
(香月洋一郎)
近世銭貨の流通—二神家伝来古銭の調査を中心として(永井久美男)
中国東南部・浙江省舟山群島の伝統的造船所と漁村—舟山本島・朱家尖島の場合(田島佳也)
文政期「異国船」防備体制と村落上層民の動向—九十九里浜の場合(岩田みゆき)
中国の女性神とその芸能—浙江省説唱芸能鼓詞『陳十四夫人伝』
(廣田律子)
軍談師の旅日記(橘川俊忠)
京都大山崎調査報告(1996年度)(中島三千男)
歴史と民俗13〈1996.9〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集13
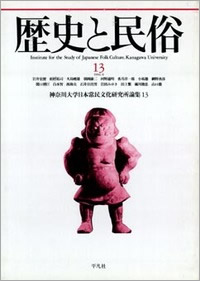
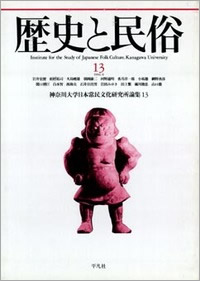
民具研究の軌跡(岩井宏實)
民具研究と博物館(柏村祐司)
民俗文化財行政と民具研究(大島暁雄)
民具研究と文化学—民具研究の将来像を求めて(朝岡康二)
『チャイニーズ・レポジトリー』誌所載清代農具図の再検討
(河野通明)
ある小社会の五十余年の「衣」の文化を通して—[書評]Barbara F.Kawakami “Japanese Immigrant Clothing in Hawaii 1185~1941”(香月洋一郎)
河童相撲考—「歴史民俗資料学」のエチュード(小馬徹)
幕末期、愛川村の諸職・職人—「農間渡世書上」が語るもの
(山口徹)
戦後の日本常民文化研究所と文書整理(網野善彦)
二神島の調査について(網野善彦)
二神家文書の概要調査と整理(関口博巨)
二神家伝来の古銭について(白水智)
二神島安養寺所蔵 大般若経の奥書について(白水智)
二神島と由利島の建築—1995年度の調査結果について(西和夫)
離宮八幡宮領大山崎荘歴史調査報告—調査の経過と史料紹介
(石井日出男)
島根県八束郡東出雲町上意東 太田一雄家文書について
(岩田みゆき)
気仙沼市・唐桑町の文書調査について(田上繁)
奥能登調査の現状と課題(橘川俊忠)


