歴史と民俗 既刊目次
※論文のデータベースは「神奈川大学デジタルアーカイブ」で検索可能です。
歴史と民俗12〈1995.9〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集12
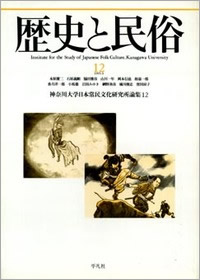
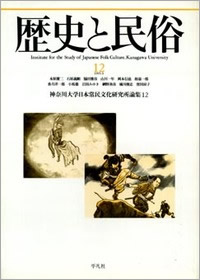
上杉領国経済と蔵田五郎左衛門(永原慶二)
海の博物館と資料(石原義剛)
小さな町村の民俗資料館—民具のあり方を求めて(脇田雅彦)
瀬戸の窯業民俗—歴史民俗資料館の在り方(山川一年)
現代社会と民具—考現学採集をめぐって(岡本信也)
岩倉市郎氏喜界島民俗調査のこと(拵嘉一郎)
民俗資料としての紙芝居—街をあるく(下)(香月洋一郎)
幼稚園のトーテミズム—日常生活の文化人類学のための序説
(小馬徹)
江梨村における宝暦元年名主交代事件と村方文書の引継について
(岩田みゆき)
時国家と奥能登地域の調査—1994年度の調査(網野善彦)
史料としての手習本(橘川俊忠)
描かれた卒塔婆(窪田涼子)
歴史と民俗11〈1994.8〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集11
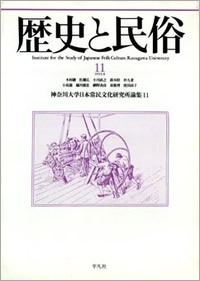
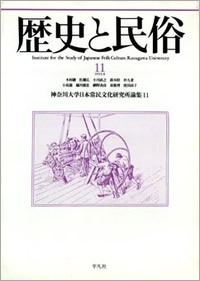
村人の日常生活と小地域(木村礎)
民具のかたちと地域の歴史—背負運搬具、特に背負梯子を中心として(佐藤広)
民具の地域研究—地域民具論の方法(小川直之)
工業技術展示品の修復作業について—日本工業大学工業技術博物館の場合(鈴木昭)
アメリカ捕鯨船の日本海来漁と竹島発見—航海日誌にみる日本海捕鯨(朴九秉)
ケニアの二重法制下における慣習法の現在—キプシギスの「村の裁判」と民族、国家(小馬徹)
日本における特殊主義の運命(5)—国学と民俗学の思想史的考察(橘川俊忠)
時国家と奥能登地域の調査—1993年度の調査(網野善彦)
北からの便り—酒屋嘉兵衛書状の紹介(泉雅博)
「赤堂」の空風輪(窪田涼子)
歴史と民俗10〈1993.8〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集10


渋沢敬三と民族学(大林太良)
異人としての民俗学者?渋沢敬三の紀行文を中心に
(アラン・クリスティ)
日本塩業研究とアチックミューゼアム(渡辺則文)
台湾の神社跡を訪ねて—旧花蓮港庁を中心に(中島三千男)
地方文人・名望家の教養—相州津久井縣上川尻村八木家の蔵書をめぐって(橘川俊忠)
時国家と奥能登地域の調査—1992年度の調査と史料の紹介
(網野善彦)
能登と北前船交易—「上時国家文書」の整理作業のなかから
(泉雅博)
近世前期奥能登における「下人」化の諸契機?時国家の「下人」を中心に(関口博巨)
時国古屋敷遺跡の発掘調査(二)—1992年度の調査とまとめ
①発掘調査と遺構の検討(河村好光)
時国古屋敷遺跡の発掘調査(二)—1992年度の調査とまとめ
②時国家古屋敷跡出土遺物に関する考察(森本伊知郎)
奥能登時国家の古屋敷について—古屋敷の位置・規模およびそこに建っていた主屋の位置・規模等の検討(西和夫・津田良樹)
歴史と民俗9〈1992.8〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集9
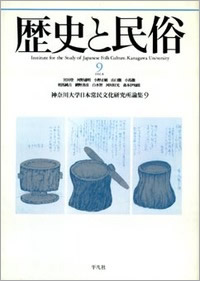
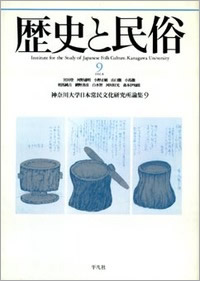
モノとタマ—民俗神道論として(宮田登)
犂を計測する—形から性能を読み取る試み(河野通明)
民具研究と「民具」の概念(小野正敏)
豆州西浦組久料村の生産と生業—海村の一類型(山口徹)
民俗学的思考と文化人類学的思考—「日照り雨の比較民族学」再論(小馬徹)
北海道と「内地」(相馬純吉)
時国家と奥能登地域の調査—1991年度の調査と史料の紹介
(網野善彦)
能登土方領下の塩制について(白水智)
時国古屋敷遺跡の発掘調査(一)—1991年度の調査
(時国古屋敷遺跡発掘調査団 吉岡康暢・河村好光・森本伊知郎・千田嘉博・浜野伸雄・金沢大学考古学研究会)
歴史と民俗8〈1991.10〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集8
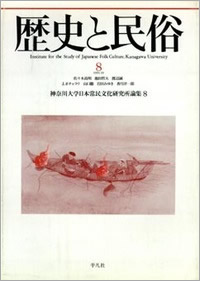
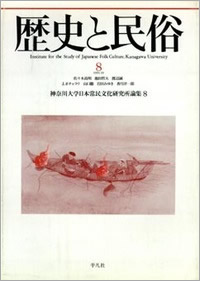
民具の比較民族学—東南アジア・オセアニアを中心に(佐々木高明)
スルメイカ釣具の伝播(池田哲夫)
瓦と木綿—東アジア的観点で(渡辺誠)
「口頭理論」と「国学」(ジョン・ボチャラリ)西伊豆土肥町の調査—海村土肥の諸相 1.土肥村の概況と諸職・職人(山口徹)
2.土肥村の土地移動の実態について—「質地奥印帳」の分析
(岩田みゆき)
街をあるく(上)—仙台市街調査覚え書き(香月洋一郎・佐藤佳子)
歴史と民俗7〈1991.7〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集7
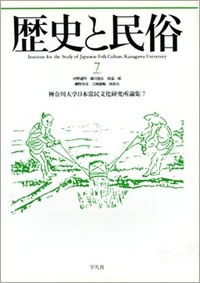
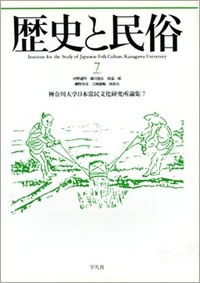
堀家本『四季耕作絵巻』の成立(河野通明)
近世村医者の本箱—大網白里町富塚家の場合(橘川俊忠)
渋沢敬三先生の思い出(拵嘉一郎)
時国家と奥能登地域の調査—1990年度の調査と史料の紹介
(網野善彦)
奥能登時国家墓地の調査—上時国家“古墓”を中心に
(吉岡康暢・浜野伸雄・近間強・森本伊知郎・窪田涼子)
奥能登時国家の建築について(二)—建設年代の再検討(西和夫)
資料・日本常民文化研究所の活動
歴史と民俗6〈1990.10〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集6
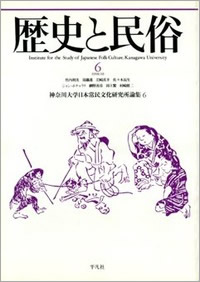
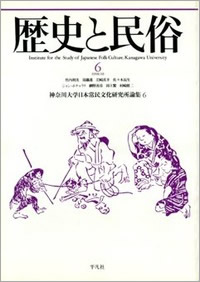
民具と山村生活(竹内利美)
山村の生活を支えた民具の体系(須藤護)
民具の保有状況から見た生活誌—福島県高郷村小ヶ峯、佐藤家の調査から(佐々木長生)
「屋敷林」の諸問題—福島県相馬地方の事例を通して(岩崎真幸)
「言霊のさだまり」—本居宣長の言語論について(ジョン・ボチャラリ)
小山家文書について 1.調査の経緯と中世文書(網野善彦)
2.近世文書と近世の小山家(田上繁)
お猿の学校(村崎修二・北川鉄夫)
歴史と民俗5〈1990.7〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集5
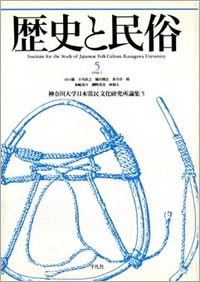
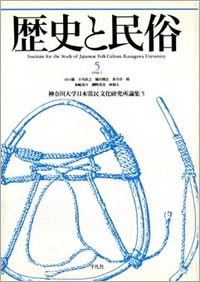
近世的雇傭の一断面—地曳網漁業を中心に(山口徹)
水利慣行と社会統合—神奈川県平塚市金目川筋を事例として
(小川直之)
日本における特殊主義の運命(4)—国学と民俗学の思想史的考察(橘川俊忠)
聞き取りという作業を通して—伝承論ノート4(香月洋一郎)
都市行政から見た民俗行事—大文字をめぐる市民・旅人の参加の「受け皿」づくり(和崎春日)
時国家と奥能登地域の調査—1989年度の調査と史料の紹介
(網野善彦)
奥能登時国家の建築について—建設年代と建設背景の検討(西和夫)
在村残存書籍調査の方法と課題2—上時国家所蔵書籍調査報告(近代)(橘川俊忠)
資料・日本常民文化研究所の活動
歴史と民俗4〈1989.6〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集4
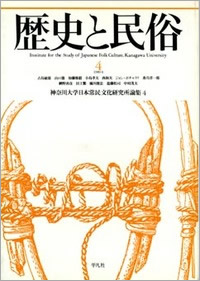
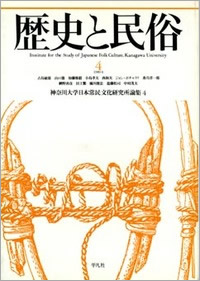
経済史家は道具をどう見るか(古島敏雄)
房総の海と生活—九十九里浜の鰯漁を中心に(山口徹)
海への視座—東京湾・富津岬にみる漁業権漁業と漁民のくらし
(加藤雅毅)
安房地方のツチクジラ漁—漁具・漁法の語るもの(小島孝夫)
近江堅田の湖上関—その位置と施設に関する絵画史料等による検討(西和夫)
「真の暦」を求めて—本居宣長と古えの時間意識
(ジョン・ボチャラリ)
フィールドで何を写すか—伝承論ノート3(香月洋一郎)
時国家と奥能登地域の調査—1988年度の文書整理の状況と史料の紹介(網野善彦)
天正期の枡と検地—前田領を中心にして(田上繁)
在村残存書籍調査の方法と課題—時国家所蔵書籍調査報告Ⅰ(近世編)(橘川俊忠)
進藤松司漁民資料(下)(進藤松司 談・香月洋一郎 編)
国際文化財保存会議に出席して(中村茂夫)
資料 日本常民文化研究所の活動
歴史と民俗3〈1988.7〉
神奈川大学日本常民文化研究所論集3
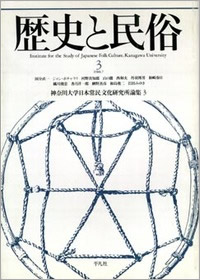
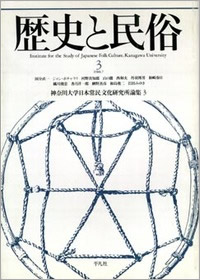
芋草の栄えた国—豊国と海上の道(国分直一)
古代を探る—チェンバレンの『古事記』研究再考
(ジョン・ボチャラリ)
中世鎌倉動物誌—都市遺跡出土の動物遺体と関連遺物からの予報
(河野真知郎)
九十九里地曳網漁業経営帳簿の組織と性格—経営帳簿の語るもの
(山口徹)
棟札に見る大工の居住地と工事場—横浜の近世社寺建築を中心とする検討(西和夫)
明治政府の社寺地処分(丹羽邦男)
都市祭礼と市民地平—大文字五山送り火における地域共同態と都市共同態(和崎春日)
日本における特殊主義の運命(3)—国学と民俗学の思想史的考察(橘川俊忠)
谷のむらの早乙女—伝承論ノート2(香月洋一郎)
奥能登時国家文書について—調査・整理の状況と新史料の紹介
(網野善彦)
「下町野之庄岩蔵」現地調査の一端(和嶋俊二)
相模原製糸業調査報告—製糸結社益進合資会社と原合名会社との往復書翰類について(岩田みゆき)
進藤松司漁民資料(上)(香月洋一郎)
資料・日本常民文化研究所の活動(1987年4月~88年3月)


