基幹共同研究「常民生活誌に関する総合的研究」 " 日常茶飯 " —日本人は何を食べてきたか
基幹共同研究「''日常茶飯''-日本人は何を食べてきたか」第8回公開研究会 終了報告
「日本人はなぜアヒルを食べないのか?
—日本と中国の自然文化誌の比較から」
菅 豊 氏 (東京大学東洋文化研究所教授)
日時:2025年6月20日(金)15:20~16:50
会場:神奈川大学横浜キャンパス9号館12室(ハイフレックス)


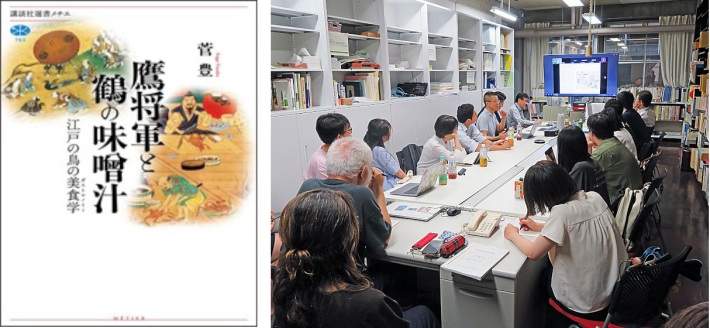
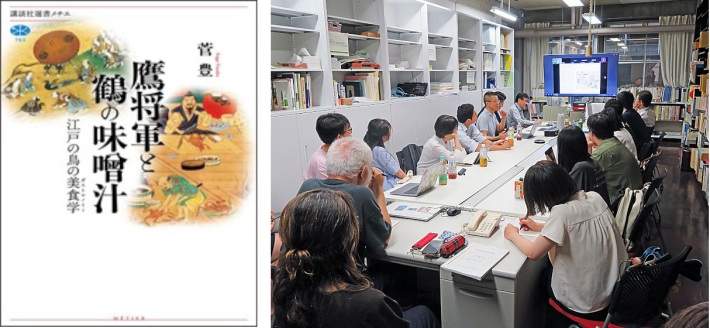
日本常民文化研究所基幹共同研究「常民生活誌に関する総合的研究」「"日常茶飯"—日本人は何を食べてきたか」第8回研究会は、公開講演会として開催された。「日本人はなぜアヒルを食べないのか?—日本と中国の自然文化誌の比較から」をテーマとして、菅豊氏が様々な文献資料や調査資料を駆使し、研究成果を発表した。
菅豊氏の講演では、かつて野鳥が日本人の食文化において重要な地位を占めていた歴史的事実、また、ガンカモ類を中心とする野鳥が食文化のみならず、政治や経済、社会、儀礼などをめぐって、魚やほかの動物たちには見られないような、複雑で高度な文化複合体を形作っていた歴史的事実を確認した。特に多彩な野鳥料理が食べられ、その味が庶民にまで届いた野鳥食文化の爛熟期である17世紀から19世紀の江戸時代の「江戸(東京)」を中心に考察したうえで、菅豊氏の講演では、現代日本人が不思議なくらいに忘れ去ってしまった日本の野鳥の食文化が、いまでは想像もできないくらいに大きな発展を遂げていた様相、そして日本人が家禽としてのアヒルではなく野生のカモを選んだ経緯や、現代の日本人がほどんどアヒルを食べない理由を克明に説明された。
菅豊氏はさらに、この野鳥の食文化と家禽(家畜)の食文化を糸口として、自ら長年の調査を踏まえて日本と中国とを比較し、自然依存/自然支配、自給/市場、共同体主義/個人主義といった両国社会の構成原理の違いを検討し、興味深い持論を展開した。
(文責:周星)


