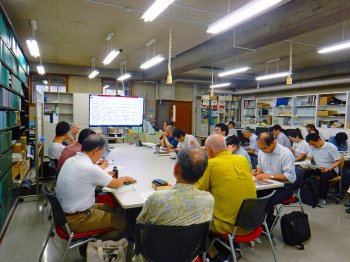基盤共同研究 日本常民文化研究所所蔵資料からみるフィールド・サイエンスの史的展開
共同研究「日本常民文化研究所所蔵資料からみるフィールド・サイエンスの史的展開」
第9回 公開研究会 終了報告
岡正雄と民族研究所設立運動
清水昭俊氏
(国立民族学博物館名誉教授 神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員)
日程:2019年6月28日(金)16:00~18:00
場所:横浜キャンパス9号館11室(日本常民文化研究所)
- 清水昭俊氏
- 研究会の様子
戦時期に民族研究所の設立に結実した岡正雄(1898-1982)の運動は、日本の文化人類学史のなかで最も注目を集めた話題の一つであろう。端的に言えば文化人類学者の戦争協力であったが、後学がそのような審判を下すことには、当事者には未知であった後年の倫理的枠組みを過去に遡って適用するという問題がある。清水氏の発表は、このような時間的遡及と重なる今ひとつの次元の時間的遡及という問題を明確にしたことで、当事者の経験に迫った学史の語りとなった。この第二の時間的遡及の問題とは、当事者には未知であった結果を前提にその行為を意味づけてしまうという問題である。
1940年末にウィーンから一時帰国した岡は民族学会の主要会員とともに国立民族学研究所設立の運動を開始したとされてきた。しかし、清水氏が丁寧に跡づけたように、当初の岡が外務省や軍に提案していたのは民族学を研究する留学生の派遣であり、文部省に提案していたのは、外務省の実践的な民族政策研究とは異なる学術的な民族学研究所の設立であった。しからば後に民族研究所として実現される計画はどこから出てきたのか。その雛形は、企画院から提案された研究所設置計画であった。これは明確に戦争国策に組み込まれた研究機関の計画であったため、そのリスクを感じ取った岡は他の学会員に相談した。彼らも軍に対する警戒心を抱いていたが、学会の活動を拡大する好機としてこの計画の受け入れを決断したというのが実際の経緯であったという。研究所設立までにはさらに紆余曲折があったが、いずれにせよ、戦争国策に組み込まれた研究機関の設立について逡巡の末に協力を選択した岡や他の学会員には、戦後になって、選択を誤ったという後悔はあっても、戦争協力への反省という感覚はなかったのではないかという清水氏の解釈は説得的である。
このような丁寧な再解釈は、当時の状況をより現実的に把握することを可能にするばかりではない。当事者の視点から彼らが生きた時代を把握できたとき、その視線は翻って、現代日本を生きる私たちの行動に向けられるであろう。たとえば、先日の出入国管理法の改正により、異文化理解について専門的な知見を有する文化人類学者の出番は増えるにちがいない。文化間摩擦の低減に文化人類学が役立つとすれば素晴らしいことだが、それは現代の国策への協力であり、その国策について外国人の労働力の搾取であるという見方もあることを忘れてはならないだろう。
研究会では、岡と比較されるG. P. マードックの活動について議論があったほか、全京秀客員研究員からは自身の資料も準備して具体的な質疑応答があった。1943年に岡の名前で翻訳が出たオズワルド・メンギーン『石器時代の世界史』上巻の実際の翻訳者はウィーン大学の後輩の都宥浩である可能性が高い。彰古書院の藤岡啓介が岡の疎開先の松本と往き来していたのは下巻の出版準備のためと考えられるが、それを裏付ける岡の日記の一部と下巻の原稿の行方についてであった。岡正雄研究への関心の深さがうかがえる一幕であった。
なお、清水氏は近年の論考(Shimizu (2017) "What Was Ethnic Research? Masao Oka and the Wartime Turn of Ethnology in Japan: a Commentary on the Papers.,” Japanese Journal of Cultural Anthropology, 18 (2): 29-61)でも戦時期の岡正雄について、とくに彼が「民族研究」というフィールドをどのように形成していったか詳細に論じている。
(文責:泉水英計)