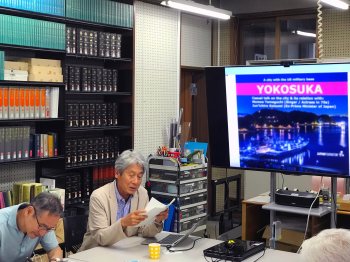基盤共同研究 日本常民文化研究所所蔵資料からみるフィールド・サイエンスの史的展開
共同研究「日本常民文化研究所所蔵資料からみるフィールド・サイエンスの史的展開」
第10回 公開研究会 終了報告
自文化のエスノグラフィー、またはアメリカの影の下の自己形成
—山口百恵と小泉純一郎、そして私のなかのヨコスカ原風景—
清水 展氏(京都大学 名誉教授)
日時:2019年7月19日(金)16:00~18:00
場所:横浜キャンパス9号館11室(日本常民文化研究所)
- 発表の様子
- 清水展氏
今年度前期最後の公開研究会には、長らく九州大学や京都大学東南アジア研究所に所属され、日本におけるフィリピンの文化人類学研究を先導されてきた清水展氏をお迎えした。氏はこれまで、『出来事の民族誌─フィリピン・ネグリート社会の変化と持続』(1990)、『文化のなかの政治─フィリピン「二月革命」の物語』(1991)などのほか、『噴火のこだま─ピナトゥボ・アエタの被災と新生をめぐる文化・開発・NGO』(2003)、『草の根グローバリゼーション─世界遺産棚田村の文化実践と生活戦略』(2013)など多数の著作を刊行されてきた。特に近年では、ピナトゥボ火山噴火後の支援に関わった経験をもとに、フィールドワークをする現地コミュニティが抱える問題に対して、人類学者がいかに関与し、「応答」していけるのかという課題にも積極的に取り組んでこられた。
今回の報告では、こうしたこれまでのご自身の研究とつながりながら、人類学者になる以前からの自己を振り返り、戦後の横須賀という特異な時空間で育った自己形成の過程が分析の俎上にあげられた。こうした問題意識には、いくつかの背景や意図、今後の研究計画があるという。
まず第1は、生まれ育った横須賀から日本文化や社会を再考する自文化の民族誌という試みである。そこには、文化人類学における比較の方法を自文化に適応すると共に、「応答の人類学」という課題のなかで自分の頭が自分の心を掘り下げる自己への応答という試みが含まれている。第2は、日本とフィリピンの比較の視点から、アメリカの影が色濃い横須賀で育った自身の精神世界を腑分け分析するという試みである。アメリカの影という意味できわめて似たもの同士のフィリピンとの比較から、横須賀で経験したアメリカを通して、戦後日本を問い返すというこれからの仕事も計画されているという。第3に、文化人類学の問題系のなかでの意義も挙げられた。他者を表象することの政治性や権力性が問題視された民族誌批判が、主にテキスト内部の問題に矮小化されたことに異を唱え、自らも見られ、書かれる対象となるという試みの意義である。
このような大きな枠組みの中で、今回の報告では、横須賀出身で自身も同時代を生きた山口百恵に焦点が当てられた。彼女の歌と実生活を跡づけ、歌の映像もあわせて紹介しながら、アメリカの影の下の横須賀と戦後日本、さらに自己形成過程の一断面が検討されていった。
報告後の質疑応答では、自文化理解や自文化研究に関して、長年のフィリピン研究を経由した上でのものは、これまでの自文化研究とどのように違い得るのかという問題や、文化人類学におけるフィールドとの距離の取り方(アタッチメントとディタッチメント)の問題などが議論された。さらに、民族誌批判でテキスト内部の問題に矮小化されがちだった視点を乗り越えるために、テキストに回収されない固有の時空間、横須賀というコンテクストから自文化を再考するという可能性が提起された。同世代の研究会参加者との間で、山口百恵に対する自らの経験と比較しながらのやりとりもなされ、あっという間に終了時刻となった研究会だった。
(文責:高城玲)
Tweet