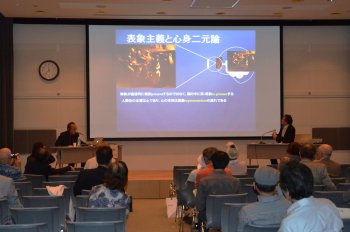FIA国際人類学フォーラム 非覇権的人類学を求めて—文化の三角測量— 日本語版詳細1日目
FIA 国際人類学フォーラム2013東京大会序言
FIA Tokyo 2013 序言 川田順造
FIA(国際人類学フォーラム)2013 Tokyo 序言
2013年9月2日、横浜で
親愛なる皆さま
FIA 2013 Tokyoでの私たちの出会いの記録を、ここにお届けします。これは、すべての部会に活発に参加された同僚、レモン・メイヤーさんのご協力で、出来たものです。
これまで常にフランス語圏の国で行われて来たFIAの、アジアのしかもフランス語圏ではない国で初めて開かれたこの会合では、同時通訳のために報告の完全原稿をあらかじめ提出していただく必要も生じました。こうした不都合にもかかわらず、世界各地から集まった人類学者たちは、互いに心を通わせ合いました。これはFIA-Tokyo 2013 の、めざましい成果の一つだったと言えるのではないでしょうか。
ご参考までに、実行されたプログラムの概要を、以下に示します。
FIA(国際人類学フォーラム)非覇権的人類学を求めて
2013年東京大会 テーマ『文化の三角測量』
主催:神奈川大学日本常民文化研究所、東京日仏会館
2013年5月16日~18日、会場:東京日仏会館大会議室
使用言語: 日本語、フランス語(同時通訳付)
【プログラム】
16日(木)18:00~20:00
フランソワ・ラプランティーヌ氏と川田順造の対論
『文化の三角測量、レヴィ=ストロース、日本』
司会:三浦信孝
17日〜18日:シンポジウム
午前の部(10:00~13:00)、午後の部(14:00~17:00)
報告は各セッション4人
座長の発言、各セッションのはじめ趣旨説明と終わりまとめに各10分、報告各25分、討論15分
17日(金)午前 『言語・コミュニケーション』
① 三浦信孝 ②ポーリン・シェリエ ③菅原和孝
17日(金)午後 『宗教・世界観』
① 蔡華 ②ベルト・ムベネ・メイヤー ③佐野賢治
セッション終了後、日仏会館内で、神奈川大学長・日仏会館理事長共催のレセプション立食パーティ、2人の歓迎挨拶
18日(土)午前 『技術・医療』
① 後藤明 ②周星 ③白莉莉
18日(土)午後 『身体・演劇・舞踊』
① 廣田律子、②野村雅一 ③ミカエル・フェリエ ④レモン・メイヤー
遠隔地のため高額な交通費にもかかわらず、FIA Tokyo 2013 にご参加下さいましたことに、改めて厚く御礼申し上げます。そして2014年ヌメアで予定されている、私たちの次の出会いが素晴らしいものでありますように、祈っています。来年、またお会いしましょう!
FIA Tokyo 2013 組織委員会事務局長
川田順造
FIA 国際人類学フォーラム2013年東京大会 - 非覇権的人類学を求めて -
2013-5-16 対論「文化の三角測量」
対論「文化の三角測量、クロード・レヴィ=ストロース、日本」
川田順造(東京外国語大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授、同大学日本常民文化研究所客員研究員)
フランソワ・ラプランチーヌ(リヨン第二リュミエール大学名誉教授)
司会 三浦信孝(中央大学教授)
文化人類学はイギリス、フランスをはじめ海外に植民地をもち、いち早く「近代化」を遂げた西洋の「文明国」で発達した学問である。文明の中心が周辺の未開文化を研究する西洋中心的人類学に異を唱え、「非ヘゲモニー的人類学Anthropologie non hégémonique」を掲げる人類学者国際フォーラムForum international des anthropologues (FIA) の東京シンポジウムが、日仏会館で開かれる。その前夜行事として、日本の川田順造とフランスのフランソワ・ラプランチーヌが、シンポジウムのテーマである「文化の三角測量」について討議する。
「文化の三角測量triangulation des cultures」は、日本の民俗学的研究から出発し、フランスで人類学とアフリカ研究を学び、フランス諸地方の伝統的職人と、西アフリカとくにブルキナファソの旧モシ王国について、長年現地研究をした川田が唱えて来た文化研究の方法である。対比的な二文化の比較に、全く異なる第三の文化を加えることにより、研究者自身の視点を是正し、それぞれの文化の隠れた性質を立体的に浮き彫りにすることを目指す。他方、哲学から人類学に転じたラプランチーヌは、クロード・レヴィ=ストロースの構造人類学anthropologie structuraleに対し、人類学に「主体sujet」概念を復活させ、エスノ精神分析学ethnopsychanalyseを起点に 「感覚的なものの人類学anthropologie du sensible」を開拓してきた。主たるフィールドはブラジルだが、最近では日本と中国に滞在した印象をもとに「文化の四角測量」の可能性を示唆している。
本対談では、川田が翻訳しラプランチーヌが書評を書いているレヴィ=ストロースの死後出版L’autre face de la lune. Écrits sur le Japon, Seuil, 2011(『月の向こう側 日本について』中央公論新社、2014年発売予定)を媒介項に、両者の「文化の三角測量」観を突き合わせ、内dedansと外dehorsから日本についての視線を交叉させる。
FIA 国際人類学フォーラム2013年東京大会 - 非覇権的人類学を求めて - 2013-5-16 対論「文化の三角測量」
クロード・レヴィ=ストロース著 『月の向う側』をめぐって
川田順造(東京外国語大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授、同大学日本常民文化研究所客員研究員)
とにかくレヴィ=ストロース先生の、日本についての勉強ぶりは凄い!というのが、この決して厚くはない本に、息切れがするほど振り回されながら、どうやら訳し終えた私の、真っ先の感想だ。それも先生のは、いわゆる「日本通(つう)」の、何でもよくご存じといった日本理解ではない。
例えば、「アメノウズメの淫らな踊り」の章での、『記紀』のうち『古事記』だけにある「因幡の白兎」という、奇妙な挿話の位置づけなど、神話の構造分析の大家の面目躍如といった趣(おもむき)がある。これまで日本人を含む『古事記』研究者の誰が、こんな解釈を思いつき得ただろうか?しかもこれは、レヴィ=ストロース先生最晩年、満九三歳の時、日本の「猿田彦フォーラム」に招かれたが、高齢のため出席できないので、おそらく前々から頭にあった構想をかなり急いでまとめて、書き送った論攷だと思われる。さらに、サルタヒコとスサノオを、やはり構造論的な垂直+水平の移動という共通性から、連続した相で捉えるという画期的な提案など、この訳書が世に送られた後での、日本の『記紀』研究者の対応が注目される。
『古事記』について、多年私の疑問のよろず聞き役をして下さった西郷信綱先生はすでに亡く、同様にかねてから諸々のご教示をいただいて来た鎌田東二さんは、「猿田彦フォーラム」を主宰して来られた方でもあり、本書刊行前にも下書きの段階で、これらの点について改めてご意見を伺おうと思っている。
創立直後の国際日本文化研究センターに招かれて行った講演「世界における日本文化の位置」に展開された、独創的な広い視野のなかでの、日本文化の位置づけの見事さ。「仙厓 世界を甘受する芸術」に示された、インド以来の仏教、そして書画についての深い理解。私との対話のなかで指摘された、ナマズ目ナマズ科に属する硬骨魚類の一種である鯰の異字癜(なまず)が、多くの種で胸鰭・背鰭などに毒の棘をもつカサゴ目フカカサゴ科の魚のナマズと、皮膚の病とを同時に意味することなど、訳者は日本人として、自文化についての不勉強を思い知らされた。
その一方で、先生のやや性急な思い込み(?)として、本書でくり返し引用されている、明治6年(1873)から明治44年(1911)にお雇い外人教師として日本に滞在した、イギリス人の日本研究家バジル・チェンバレンの”Things Japanese”(1890年初版、高梨健吉訳『日本事物誌』全2巻、平凡社東洋文庫1969、271〜273頁)にある短い一項目“Topsy-turvydom”「あべこべ」で、著者チェンバレンも「知人の婦人が知らせてくれたこと」という留保付きで挙げている「日本の婦人は針に糸を通すのではなくて、糸に針を通す」ということを、レヴィ=ストロース先生はそのまま、本書の何カ所かで挙げておられるが、先生はこれを、手で縫い物をするヨーロッパと日本の女性について、確かめられたのだろうか?日本人で裁縫の経験が豊かな、小学四年生から「運針」を習ったという年配の女性何人かに私が訊ねた限りでは、これとは反対に、針穴に糸を挿し入れるという答えだった。
逆に私が1964年の学生時代、ヴェネツイアから汽車でウィーンに行ったとき、隣の座席に座ったイタリア人女性が、縫い物をしていて、立てた糸に針穴を近づけて糸を通すのを、好奇の目で見たことを、私ははっきりと憶えている。この慣習のヨーロッパと日本における違いなどは、その気で調べれば直ぐ明らかにできることではないだろうか。
鋸を押すか引くかについても、先生のやや一般化され過ぎた思い込みがある。中国を始めユーラシア大陸のあちこちで、縦に木目の通った柔らかい針葉樹の多い地帯では、引いて使うことが確認されている。鉋のように削る道具にいたっては、西洋の極めて広い範囲で、伝統的樽造り職人は前傾した台に乗せた側板用の板を、ゆるやかに湾曲し、両側に把手がついた独特の「プラーヌ」という道具で、刃を手前に引いて削る。私がフランスのオーベルニュ地方で車大工の仕事を見せてもらったときも、作業台に万力で固定した木の素材を、立位のまま両手で両端を持った平らな削り器で、おおまかな下拵え作業のときは押して削るが、細やかさが求められる仕上げ作業では、同じ道具で逆に引くのを、私は実際に見て写真も撮っている。
土器の成形轆轤のはずみ台を、反時計回りに右足で蹴り出すことが、日本以外で、琉球、中国、トルコから、スペイン、フランス、ノルウェーで一般的であることは、私自身確認しているが、同時に、中国の四川省の土器造り工房で観察したところでは、大きい甕の外側を少しずつ回して仕上げる作業では、左足で時計回りに少しずつ回転させるのを、私は実際に見ている。西アフリカ内陸部のマリで、人間が深前屈姿勢で土器の周りを回って成形する社会で、時計回りか反時計回りか、前進か後退か(速いか遅いか)、成形する土器の形状によって、左右の手(利き手)をそれぞれ土器の壁面の内側・外側のどちらに置くか等々を、詳しい一覧にしてみたが、きわめて合理的な組み合わせとして考えられていることが分かった。土器の成形に関しても、対象により、成形の段階によって、決して杓子定規ではない身体技法の適用がある。同様のことは、西部インド、グジャラート地方での機織りについても、私は実感した。このあたり、先生のお考えは、現地での直接の見聞に基づいているというよりは、かなり観念的に一般化されているのではないかと思われてならない。
先生は、日本の陶工は、はずみ車を左足で蹴り出して時計回りに回転させると、直接ご覧になっていないのに、想像で断定しておられるが、実際は右足を内向きに蹴って時計回りにするのであることは、最後の章「川田順造との対話」のなかでも、私が補足説明している通りだ。
ヨーロッパでも中国でも広く用いられて来た、軽くて使いやすい枠付き鋸が、刃に使う鉄の分量としても経済的であるのに、日本では室町時代に、二人遣いの大型枠付き鋸が、縦挽き用にいったん導入されたのに定着せず、鉄の使用として不経済きわまりない大鋸(おが)が縦挽きに用いられたことは、平座位の作業姿勢を好む日本の職人の作業姿勢にも関係しているかも知れない。
ただ、枠付き鋸が日本で定着しなかった理由について、日本の大工道具研究家でご自分も大工仕事を実践しておられた故村松貞次郎さんは、道具と使い手の身体との一体感を重んじる日本人の伝統を考えておられて、この点はレヴィ=ストロース先生の解釈と結果としては一致する。だが先生の最晩年、誕生日のお祝いに、日本の大工道具について指物師大館年男氏が英語で書いた “Japanese Woodworking Tools: Their Tradition, Spirit and Use”, First Linden Publishing Inc. U.S.A. 1998を、かねてから親しくお付き合いしている神戸市の竹中大工道具館の元主任学芸員渡邉晶さんから教えていただいて取り寄せ、竹中大工道具館の図録や英文資料と一緒にお送りしたところ、竹中大工道具館のことは、ご存じなかったというお手紙をいただいて、びっくりした。地方で個々の木工職人(それも実際には、他の分野の職人と合わせてもごく少数の人を、先生は訪問されたに過ぎない)を訪ねる前に、ここで展示やビデオをご覧になって、全般的な視野をおもちになっていれば、職人訪問もさらに効果的だったろうにと、悔やまれる。
同様に、先生を招聘した機関の、かなり紋切り型の手配のためにかえすがえす心残りなのは、先生は五度も、それぞれかなり長く訪日しておられながら、そしてご自分の著書の一冊の題を『離見』 “Regard éloigné” (みすず書房から出ている三保元 —— 石坂財団招聘による先生の二日間にわたる記念講演「現代世界と人類学」を、先生が一カ月前に全草稿を通訳のためにと送って下さったのを私が届けたのに、同時通訳者は下読みはしないと敢えて目を通さず、当日滅茶苦茶な同時通訳(?)で台無しにしたのもこの訳者だ —— による邦訳では『はるかなる視線』と訳され、“éloigné” というフランス語は、「はるかな」ではなく「意図して引き離した」という意味であることも理解しない、訳者のフランス語の初歩的な誤りによる、ひどい誤訳になっているのは残念だ。私が直接先生に伺ったところでも、世阿弥の「離見」のフランス語訳だと断言された)とまでして、能に深い関心をもっておられながら、日本でお能をご覧になったのはただ一度、初めての来日時の日本到着直後に、『高砂』をご覧になっただけということだ。
この時招聘機関は、すでに『高砂』を手配した後で、お能に詳しくフランス語にも堪能な渡邊守章さんに、案内役を急遽依頼して来たのだという。渡邊さんは、前以て相談があれば、1977年当時は惜しまれつつ早世した観世寿夫もまだ存命であり、他に可能性があったのに、と悔やんでおられた。
しかも、初来日早々先生がご覧になった、この唯一の能が、翁と嫗が熊手と箒を持って登場し、松の木陰を掃き清めるという、この時の来日の中心課題「労働の観念と表象」に偶々直結するものだったから、先生の印象はなおのこと強烈だったのだ。
本書の二番目に納められている、パリで開かれた日本文化をめぐる日仏合同のシンポジウムでの、締めくくりの講演「月の隠れた面」で、先生は「能のある上演のとき、ここにおいでの渡辺守章教授は私に、能では労働はまさしく詩的な価値をもっている、それは労働が人間と自然のあいだの交信の一形態を表しているからだと、私に繰り返し教えて下さいました」と、その席におられた渡邊さんを道連れにして、だが実際に演能を観たのは『高砂』だけだったということには触れずに、『高砂』の印象をやや強引に一般化しているのは、先生らしい、微笑ましい見栄であるのかも知れない。
関連して思い出すのは、『悲しき熱帯』で、先住民への「お土産」や、それと引き替えに博物館のために収集した品々を、牛やトラックに満載して、ブラジル中部を南から北へ縦断する大旅行の記述でも、例えば最も長く滞在したと思われるナンビクワラの居住地で、僅かの徴候も鋭く捉えた見事な観察の結果を記述しているが、何日間ナンビクワラのところにいたかについては、一言も触れていないのは、調査記録として不可解ですらある。前後関係からの私の見積もりでは、せいぜい二週間程度でしかなかったのだが、このときの広域調査では、いわゆる人類学的な参与観察などは、到底できない状況だったことは、先生ご自身が調査の弱点として、強く感じておられたに違いない。
それでも、何月何日にどこに着き、何日間滞在して調査という最低限のデータは、少なくとも要所要所で記して置くのが、調査記録の基本ではあるだろう。もっとも、時系列を一切無化した構成の上に、『悲しき熱帯』という「作品」全体が成り立っていることを考えれば、日付のない調査記録もあり得て良いとも言える。
私はこのときの広域調査は、レヴィ=ストロース先生の構造分析の特徴である、モデルの変換による構造の発見という方法を構想する上で、大きな意味をもったのではないかと思う。その点では、ベーリング地方から南米南端まで、異なる生態系のなかをかなり短期間のうちに人間が移動・展開して、それぞれの文化を形作った南北アメリカ先住民文化は、レヴィ=ストロース流の構造分析にとって好適な場であり、例えば住民移動の歴史も、移動と生態系との関係もはるかに複雑なアフリカ大陸の文化に、構造分析を適用してもうまく行かないことが多いのと対比させうると思う。
ただ、この時の広域調査を下地に、レヴィ=ストロース先生は、いくつかの社会で長期間の住み込み調査をしたいと考えていたが、フランスへ帰国後まもなく第二次大戦が勃発して、それが不可能になったと、私に話して下さった。第一次大戦で帰国できなくなったために、はからずもトロブリアンド諸島で長期間の調査をすることになったマリノフスキーとは、世界大戦と長期調査=参与観察の関係では、逆の立場に置かれたことになる。
終わりに、先生の日本での食体験をめぐる「ここだけの話」。ブルゴーニュの先生の別荘でのある夜、先生は私に、刺身も泥鰌鍋も鯉の洗いも美味しいと思って食べたが、日本で食べられなかった唯一つのものは何だったか分かるかと質問された。私が答えられずにいると、「馬肉ですよ」とおっしゃった。深川にも「さくら鍋」の老舗があるので、私もお連れしようかと思っていたし、ほかでも誘われたことがあったのであろう。先生は、ヴェルサイユのブルジョワの家庭に育ったので、馬は人間の高貴な友であるという観念が、幼時から染みついているためだと説明して下さった。
ヨーロッパでも、フランス、イタリア、東欧では馬肉食は一般的だし、まだ農村で馬を盛んに飼っていた1960〜70年代には、パリのあちこちに、金色の馬の首を看板にした馬肉専門店があって、他の一般精肉店とは定休日を変えて営業していた。パリ北部のラ・ヴィレット街の牛豚の屠殺場と別に、南の十五区には、馬専門の屠殺場もかつてあり、馬に目隠しをした屠殺シーンの写真がついた古い絵はがきを私は持っている。ミンチにした生の馬肉に、生卵の黄身や香辛料を入れて練った「ステーク・タルタル」は、パリのレストランでもよく食べたし、地方のフランス人友人宅でもご馳走になった。
だがイギリス人は馬肉を、決して食べないという。レヴィ=ストロース先生とは、馬肉食の起源についてもいろいろ議論したが、納得の行く結論は出なかった。先生は、文化相対主義には限界があるという自覚をもつことが、極めて大切だと言われた。
このことに関連して興味深く思うのは、先生ほど個人についても、国や文化についても、好き嫌いの激しかった人も稀ではないかと思う。これについてもさまざまな思い出があるが、長くなるので、別の機会にゆずる。
先生が亡くなられた翌年、私は先生の別荘と同じブルゴーニュ地方のビブラクトにある、紀元前2〜1世紀の住民ゴール人の広大な集落遺跡の野外博物館を訪ねる機会があった。館長の説明では、ゴール人は軍事目的で馬を多く飼っていたが、馬肉を食べるのは、首長に限られた特権だったと説明してくれ、私はそれなりに納得した。このことをレヴィ=ストロース先生は、ご存じだったかどうか、今となってはお訊ねする術がないのが心残りだ。
ともあれ、これだけ内容充実し、多様性に富んだ論文の数々が、これまで日本語だけでしか刊行されていなかったか、極めて範囲の限られた展覧会パンフレットや、学術的内部資料のような形でしか、世に知られていなかったということは、ご自分の業績のまとめには無頓着で、常に先へ進むことしか念頭になかった、探求心の塊のようなレヴィ=ストロース先生の生き方そのものを象徴しているだろう。先生の学恩を受けた日本の一人類学徒として、この書をどうやら訳了できた幸せを思う。
胆嚢癌摘出の手術後、四週間の入院中に翻訳を終えた退院前夜
2013年4月30日、日本赤十字医療センター、716号病室で
川田順造
非覇権的人類学を求めて - 文化の三角測量 -(日仏同時通訳)
開催日時
第1日目 5月17日(金) 10:00~17:00
第2日目 5月18日(土) 10:00~17:00
主催 神奈川大学・公益財団法人日仏会館
会場 日仏会館ホール
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-9-25
Tel: 03-5424-1141
<プログラム>
第1日目 5月17日(金)
【午前の部10:00~13:00】 言語・コミュニケーション
座長:ミカエル・フェリエ
三浦 信孝 / 言語の三角測量:中江兆民の『社会契約論』の漢文訳をめぐって
ポーリン・シェリエ / 日本とブラジルの出会いについて:言語的・文化的再構成の一調査
菅原 和孝 / 身体化された経験としての言語交換の論理と秩序
–狩猟採集民グイにおける日常会話の分析 –
【午後の部14:00~17:00】 宗教・世界観
座長:フランソワ・ラプランティーヌ
蔡 華 / 神・人・魔
ベルト・ムベネ=メイヤー / ガボンの宗教文化の三角測量
佐野 賢治 / 仏教受容の民族性と民俗性
第2日目 5月18日(土)
【午前の部10:00~13:00】 技術・医療
座長:レモン・メイヤー
後藤 明 / オーストロネシア世界における海上運搬具の技術革新にみる技術性と傾向 -フランス技術人類学の諸概念の適用可能性について‐
周 星 / 東アジアの端午節 -薬物を中心にして-
白 莉莉 / 生業形態の変化と信仰 -モンゴル族のオボー信仰を事例に-
【午後の部14:00~17:00】 身体・演劇・舞踊
座長:レモン・メイヤー
廣田 律子 / 身体コミュニケーションによる伝承 -祭祀儀礼の場から-
野村 雅一 / 自己演技と身体 -認知症からの問いかけ-
ミカエル・フェリエ / レヴィ=ストロースと日本 -見る、聞く、読む、恋愛の身体・断章-
レモン・メイヤー / 仮面文化の三角測量 (アフリカ、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニア)
2013-5-17 シンポジウム「非覇権的人類学を求めて‐文化の三角測量‐」(第1日)
「言語の三角測量」 - 中江兆民の『社会契約論』の漢文訳をめぐって - 三浦信孝(中央大学)
三浦信孝(中央大学)
私が川田順造の名前を知ったのは、レヴィストロースの『悲しき熱帯』の訳者(1977)としてよりも前に、まだ30代で書かれた『マグレブ紀行』(1971)によってである。 間近でお会いしたのは、1991年にアカデミーフランセーズのフランコフォニー大賞を受けられた折、日仏会館でフランス語の講演をされ、私がその同時通訳をつとめたときである。無文字社会における「音」を中心にしたコミュニケーションの研究は、音声中心主義を批判してエクリチュール(文字言語)の理論を展開したジャック•デリダの対極にあるように思われ、興味を引かれた。私が「多言語主義」についての論集を企画したとき、アフリカニストとして豊かな言語経験をもつ川田氏に寄稿をお願いした(三浦編『多言語主義とは何か』 藤原書店、1997)。そんな経緯で今回人類学者ではない私にお声がかかったので、「言語の三角測量」について話すことにした。
「三角測量」の方法を、私はフランス・アメリカ・日本のデモクラシーの理念型の三角形や、フランスの共和主義・アングロサクソンの多文化主義・カリブ海のクレオールという統合モデルの三角形に自由に適用してきた。しかし今回とりあげるのは、フランス語を介した日中間対話の可能性という言語の三角形である。
日本語訳がある大著『中国思想史』の著者アンヌ・チャン教授(コレージュ・ド・フランス)との最近の交流にもとづき、中江兆民によるルソー『社会契約論』(1762)の漢訳を中心に話すが、ルソーの翻訳者である兆民の『三酔人経綸問答』(1887)には仏訳があるだけに、思想の伝達と文化間対話における翻訳の役割についても触れる。
「日本とブラジルの出会いから」 - 言語・文化的再構築の一調査 - ポーリン・シェリエ(エクス・マルセイユ大学)
ポーリン・シェリエ(エクス・マルセイユ大学(フランス))
日本とブラジルは、移住の歴史によって結びついている。まず1908年に日本人のブラジル移住が開始され、1980年代末頃からは、日系ブラジル人が日本への移住を開始することとなる。以来、両国の文化の衝突が、まず最初にブラジル、次に日本において見られるようになった。そこから生まれたのが文化的再構築の数々であり、今日ではどちらも「日系ブラジル(の)」と称されている。ここでは、日系ブラジル人たちが使用する言語に注目してみたい。ブラジルにおいて、日系移民たちの話す日本語が、ポルトガル語との接触によって変形する一方、日本で日系ブラジル人たちが話すポルトガル語もまた、日本語の影響を受けたのである。これら双方の日系ブラジル語は往々にして、少数派の不完全な言語、「出稼ぎ労働者」や「移民」の言語として、否定的に受け止められがちである。しかし、「エスニック・メディア」と呼ばれる在日ポルトガル語メディアにおいては、「日本語化した」ポルトガル語の使用が評価されることもある。
本発表では、出稼ぎ労働者の言葉の調査を通して、言語・文化的再構築の過程を明らかにしてみようと思う。その過程は、日系ブラジルという第三の文化の出現に至る道筋であり、その文化は、固定することなく常に発展し続ける。そして、この文化の理解には、日本・ブラジル・日系ブラジルという三つの言語・文化的道具を「使いこなす能力」が必要なのである。
「身体化された経験としての言語交換の論理と秩序」 - 狩猟採集民グイにおける日常会話の分析 - 菅原和孝(京都大学)
菅原和孝(京都大学)
西欧の文化的覇権の一端は、命題の陳述によって世界を写像することに言語の本質を求める偏った言語観に基づいている。その基軸には、言語行為と相互行為の双方における規則中心主義的な理論がある。だが、音声による対面交通にこそ言語の根源はある。本発表は、南部アフリカ狩猟採集民グイ(Gui)の日常会話を分析することによって、二点を明らかにする。
- 利得に関わる交渉過程は、適切性条件に基づいた発語内行為の「玉突きモデル」によってではなく、複数のムーブ(動かすこと=ゲームの「手」)の累積的効果を照らす「秤モデル」によって理解しうる。また、ムーブを連鎖させる「論理」は、交渉を身体的な「喧嘩ごっこ」と類比される遊戯へと浮遊させる仕掛けとなる。
- 欧米の会話分析で相互行為の秩序を支える根幹とされてきた「順番どりシステム」の限界を指摘し、長く頻繁な同時発話が無秩序の徴候ではなく、文脈上の意味に充填されていることを論証する。
「神・人・魔」 (とその媒介) 専門用語としての「宗教」はいまだ有用か? 蔡華(北京大学)
蔡 華(北京大学)
四種類の身体表現システム(中国少数民族のナア族、中国の漢民族、フランス人、ブルキナファソのサモ族)の比較研究の結果、超親族関係の全てのシステムは一連の信仰に基づいているという結論に達した。
この結論の理論的争点として、次のような点が挙げられる。まず、「聖なるもの」を構成するのは宗教への信仰だけではないということである。超親族や、政治や経済に対する信仰、つまりデュルケームによって「俗なるもの」とされたものなども同様に「聖なるもの」とされているようであり、その結果、次に、人類学や社会科学における従来の四分野(家族、政治、経済、宗教)もまた見直しの対象とされているのである。なぜなら、宗教生活や家族生活、そして政治や経済生活の基礎にはそれぞれ一連の信仰が存在するからである。従って、「宗教」を一連の信仰や象徴の総体と理解することはもはや適切ではないことがわかる。
いくつかの宗教生活形態の分析を通して、「宗教」という言葉を専門用語として使い続ける場合の使用範囲縮小の必要性を示してみたいと思う。
四つの団体表象のシステム [ナア(中国)、ハン(中国)、フランス、サモ(ブルキナファソ)]を比較研究することで、発表者は、一般の親族関係を超える関係(méta-parenté)のいかなる体制も一連の信仰に基づいているという結論を得た。
こうした結論の理論的な賭け金としては以下のようなものが挙げられる。第一に、宗教という語にあてがわれるさまざまな信仰だけが、「聖なるもの」を構成するわけではないことである。メタ親族に対する信仰や政治・経済への信仰、すなわち、デュルケムによって「世俗的」と見られたものに対する信仰もまた、「聖なるもの」のようなのである。第二に、人類学や社会科学における古典的な四つの領域の区分(家族、政治、経済、宗教)もまた、疑問に付されていることが明らかとなる。なぜなら、宗教生活だけでなく、家族生活や政治・経済の生活もそれぞれ一連の信仰を基盤としているからである。その結果、「宗教」をさまざまな信仰が寄り集まったものとして定義したり、象徴の総体として定義したりすることは適切でないことが分かる。
いくつかの宗教生活の形態を分析することで、「宗教」という語をテクニカル・タームとしてそのままにしておこうとするならば、この語の意味を縮減しなければならなくなることを示したいと思う。
「ガボンの宗教文化の三角測量」 ベルト・ムベネ=メイヤー(サンテグジュペリ大学)
ベルト・ムベネ=メイヤー(元ランバレネ市長・サンテグジュペリ大学(ガボン))
今回は、パリ第一大学で1983年に発表した博士論文の結論を用いて、文化間の諸関係に現在適用されている人類学的概念の有効性について再考してみたい。例としては、我が国ガボンにおける異なる宗教文化の出会いを紹介する。レヴィ=ストロースの用語でいうところの変化に抗する「冷たい社会」という見方とは反対に、「熱い」という形容詞を用いて、ガボン社会全体が変化を受け入れる社会であることを明らかにしたい。宗教の面と、国内における三角測量を通して示してみよう。ガボンには異なる宗教文化が出会ってきたという歴史があるが、川田順造氏の言葉を借りればそれらの文化は「断絶」していたのであって「連続」していた訳ではないのである。
三角測量に関しては、必ずしも三大陸を引き合いに出す必要はないと思っている。なぜならガボンを例に取った場合、アフリカの数々の宗教の中に西洋のキリスト教が入ってきた時の事例を参照したり、また中東のイスラム教への転向についても言及できる。しかし特に強調したいのは、古代エジプトがガボンの信仰に与えた影響の大きさで、これは我々が解釈し実践する宗教の世界を長期間形成してきた第三の宗教的基軸とも言える存在である。これら3つの衝突事例から得た教訓を、自らの結論としたいと思う。
(レヴィ=ストロースの用語でいう、変化に抗する「冷たい社会」という観点を私はとらない。むしろここで示したいのは、変化に開かれた社会のことを指すのに「熱い」という表現を残すのであれば、ガボンの社会は全体的に「熱い」ということである。このことを宗教的な面から示すとともに、国内という次元で三角測量を適用することで示したい。宗教文化同士の接触は、ガボンで歴史的に起きたことだが、川田順造の言葉を使えば、それらは「断絶」しているのであって、「連続」しているものではなかったのである。
三角測量に関して、私は必ずしも三つの大陸に呼びかける必要はないと考えている。ガボンの例を挙げれば、アフリカのさまざまな宗教の中に西洋のキリスト教が到達したことを参照することができるからだ。また、中東のイスラームに対する転向といったことも例に挙げることができるだろう。しかし本発表でとくに喚起したいのは、古代エジプトがガボンの信仰に及ぼした多大な影響である。私たちが実践し構想する宗教的世界を長く形作ってきた、第三の宗教的軸について議論すべきであろう。結論では、こうした三つの衝突から教えを引き出してみたいと思う。)
「仏教受容の民族性と民俗性」‐虚空蔵と地蔵菩薩信仰を事例に‐ 佐野賢治(神奈川大学)
佐野 賢治(神奈川大学常民文化研究所)
平安時代末に成立した『今昔物語集』は、天竺(インド)・震旦(中国)・本朝(日本)三国の仏教説話を収録している。インドで創唱された仏教は、西方には展開せず、東漸し極東の日本まで伝播する。お釈迦様からの聞書きの形をとる『仏典』はじめその教理は、その間、宗教者・民俗との関係の中で取捨選択され、さらに加えられ(『偽経』)、それぞれの民族における仏教民俗を形成した。ここでは仏教学・仏教史の立場ではなく、仏教受容の有り方を指標にし、それぞれの民族性、加えて一民族・一国内における地域的展開ともいえる民俗性をとらえられる有効性を、その視角と具体的事例を提示しながら試みる。
- 比較の基準 連続性 → 比較民俗研究 (民俗学)
非連続 → 文化の三角測量(人類学) - 民俗信仰の4類型 ①固有信仰 ②民間信仰 ③民俗宗教 ④民族宗教
- 仏教民俗のとらえ方 ・①仏教民俗 a+b=ab ②修験道a×b=c
・教理(普遍的 — 宗教者(歴史的)-民俗(類型的?) - 虚空蔵菩薩信仰と地蔵菩薩信仰の日本的展開